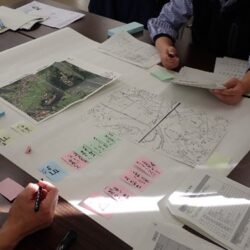2025.03.31 [ その他 ]
長野地域への移住ってどうですか?移住の先輩にきいてみた!【長野県高山村編】
長野地域振興局では、長野地域9市町村への移住や二地域居住を推進しています。今回の話し手は、2016年11月に長野県高山村へ移住した村内倫子さんです。(この記事は2024年12月に行った取材に基づき作成しています。)

高山村で養鶏業を営む村内倫子さん。平飼い養鶏で育った元気いっぱいの鶏に囲まれ、忙しくも賑やかな日々を送っている。
~高山村に魅せられて~
――本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、村内さんのご出身は熊本県なのですね。
はい。生まれも育ちも熊本の八代です。八代亜紀さんの出身地、あの辺りです。
――ご出身は随分遠方ですが、移住をしようと思ったきっかけはなんだったのでしょうか。
長年全然違う仕事をしていたのですけれど、 非常にハードワークで体を壊しまして…。その仕事が嫌だったわけではないのですが、一生の仕事にするのは難しいというか、やはり体が資本なので大事だなと思いました。そこで、もっと自然に近い暮らしをしていきたいなと考えました。
それまではいろいろな土地を転々として仕事していたんですけれど、どこか終の住処を決めて、そこで自然と関わり合いながら暮らしていけたらなと思って。そんな中で浮かんだのが長野県だったんです。
移住と言うと話が大きくなってしまうけれど、以前からいろいろな土地に住んできたので「どこに住もうかな」と、割と気軽な感覚で長野県へも来たんです。実は全然、役所とかでの相談もしてなくて。「何に出会えるかな」という、まっさらな心持ちで長野へ来たんですよ![]() 。
。

――『高山村』に目をつけたきっかけは何だったのでしょう。
長野に来た当初は、移住先のあてもなかったので、長野駅の近くでゲストハウスに滞在しました。車もなかったので、長野駅の近くだと動き回りやすいかなと思ったからです。そこで「”ピン”と来る移住先を見つけよう」と思っていました。そんな中、4ヶ月ほど経った頃、知人から「高山村で イベントがあるから、ちょっと手伝いに行かない?」という誘いを受けました。その時は高山村を全く知らなくて…![]() 。「1日で帰ってこられる場所なのかな?」みたいな感じでした(笑)。YOU游ランドでのイベントだったんですけど、お手伝いが終わって高山村から長野市へ帰る時に、善光寺平を見下ろす坂道を下る風景が素晴らしくて
。「1日で帰ってこられる場所なのかな?」みたいな感じでした(笑)。YOU游ランドでのイベントだったんですけど、お手伝いが終わって高山村から長野市へ帰る時に、善光寺平を見下ろす坂道を下る風景が素晴らしくて![]()
北アルプスを望んで毎日を暮らせるのがすごく嬉しいというか、もう”ピン”ときてしまって![]() 。そこから、「高山村になんとか住めないかな」と思っているうちに、とんとん拍子に「住んでもいいよ」という家が見つかりました。
。そこから、「高山村になんとか住めないかな」と思っているうちに、とんとん拍子に「住んでもいいよ」という家が見つかりました。

果樹畑の奥に善光寺平を望む高山村の美しい風景。村内の標高差は1600mにもなるため、桜や紅葉の見頃が長いのも高山村の風景の特長。(写真提供:高山村)
――移住の決め手は美しい『高山村』の風景だったのですね。
入口は「美しい風景」ですね。ただ、何が決め手かと言われると、高山村の「環境」です。温泉もあるし、果物はもちろん、ワイン、チーズ、生ハム、ジビエ…美味しいものがいろいろあって![]() 。
。
それと本当に「人」もいい。知り合った人は、皆さんことごとくいい方ばかりでした。「あぁ、ここは本当にいい土地だな」と思いました。「風景」の美しさを入口に、次は「環境」、そして「人」ですね。

温泉地としても有名な高山村。信州高山温泉郷としても知られ、泉質や趣の異なる様々な温泉を愉しむことができる。(写真提供:高山村)
――長野県や『高山村』にご友人や知人がおられたわけではなかったのですね。
まったくいなかったです(笑)。うまく説明できないですが、偶然にご縁が重なりましたね。やっぱりピンと来たところに進むのが正解だなと思っています![]() 。
。
――ご家族などは、村内さんの移住を知って、驚いていたのではないですか。また、知らない土地への不安などはなかったのでしょうか。
周りは、「またなんかやってるなぁ。今度はどこ行くの?」みたいな(笑)。「そのうち帰ってくるんじゃない」くらいの気持ちだったみたいです。
でも私自身は、心配や不安はなかったです。むしろ「新天地にGO![]() 」という感じでした。
」という感じでした。
――高山村以外にも長野地域での移住先候補はあったのですか。
七二会など長野市の中山間地域もいくつか見ていました。でも、高山村を知ったとき、すごく便利だなって改めて思いました。車を使う際は高速のインターチェンジが近いし、電車なら長野駅も近いし※。『ちょうどいい田舎』だなと思いまして。
明るい感じの開けた土地で、山の上から、扇状地になっている山裾の方まで全部が高山村なんですよ。すごくバラエティに富んだ土地だなというのが印象的でした。
※上信越自動車道須坂長野東ICから高山村中心部までは車で約25分。長野駅からは車で約40分。長野電鉄須坂駅からは路線バスも運行されている。
~『ちょうどいい』『明るい』田舎、高山村の生活~
――実際に住み始めた当時、村への第一印象はいかがでしたか。
先ほどもお話ししたように『ちょうどいい田舎』、『明るい田舎』という感じでした。何と言いますか、「寂しすぎず、賑やかすぎず」です。
例えば小布施町でたくさんの人を横目に見て、そこから10分くらい車を高山村へ走らせるだけで「ぜんぜん人いないなあ」って。村民が少ないのも悪いことではなく、私はいいなって思っています。村長さんは困るかもしれないですけどね(笑)。
――須坂市や小布施町などの市街地も近いのですね。日常の買い物などは不便ありませんか。
全然困っていないです。買い出しは大体、車で須坂市か小布施町へ行きます。
――生活の足はやはり車になりますよね。通勤通学時間帯や休日は道が混雑するという話も聞きますが。
生活の足は車![]() ですね。でも、渋滞ですごく不便とは感じないです。「この時間帯はあの辺が混むな」というのもわかってきますし、混まない道も覚えてきます。大丈夫ですよ
ですね。でも、渋滞ですごく不便とは感じないです。「この時間帯はあの辺が混むな」というのもわかってきますし、混まない道も覚えてきます。大丈夫ですよ![]()
――高山村の生活にすごく馴染んでおられるようにお見受けします。ちなみに、ご出身の熊本と比べ、日常生活で一番ギャップを感じたことは何でしょうか。
「ガソリン高いな![]() 」って思いました。車がないと暮らせないのは、熊本もそうだったのですが、この辺りはとにかくガソリン価格が高くって…
」って思いました。車がないと暮らせないのは、熊本もそうだったのですが、この辺りはとにかくガソリン価格が高くって…![]() 。どうにかならないかなと思いますけどね(笑)。冬場は灯油も使うし、燃料費はかなり厳しいなと思います。生業にしている養鶏も、本当に車が大事なんです。だから、この点は声を大にして言いたい
。どうにかならないかなと思いますけどね(笑)。冬場は灯油も使うし、燃料費はかなり厳しいなと思います。生業にしている養鶏も、本当に車が大事なんです。だから、この点は声を大にして言いたい![]() 。
。
――物価はどうですか。
食に関してはすごく安いと思います。私が生産者さんに近いからというのもあるとは思いますが、野菜、果物は良いものが本当に安く手に入る。野菜、果物、とにかく「食」には満足しています![]()

果樹栽培が盛んな高山村。代表格の「りんご」をはじめ、様々な果物の宝庫。ワイン用ブドウのシャルドネなども栽培され、村内には6軒のワイナリーも。(写真提供:高山村)
~『鶏を思い、愛する。』村内さんの養鶏~
――ところで、お仕事は養鶏をされているのですね。過去に関係のあるお仕事をされていたのですか。
全く経験はなかったです。養鶏を始めるきっかけは、最初に住み込んでいた長野駅近くのゲストハウスのオーナーが、パーマカルチャーという自給自足の暮らしのようなスタイルで、畑や狩猟などいろいろされている方でした。その方が「平飼い養鶏※をやりたい」と。でもお住まいが、市内の住宅街だったので、鶏はなかなか飼えなかったんです。そんな折に、「高山村なら鶏を飼えるよね」って声をかけてもらいました。オーナーがお金を出して小屋を建てて、雛から飼育するのは私が担当みたいな。仕事の一環で私が飼育を引き受けて、鶏が産んだ卵の半分を納めて、半分は私にといったような感じでした(笑)。雛から育てる中で、高山村の中でいろいろな方から餌をいただいたりしたんです。なので、鶏が卵を産んだら協力して下さった方にお礼としてお返ししたりしていました。
そういった中で、日本の養鶏にはすごくいろいろな課題があると思うようになって、「本当に自分が納得できる卵を販売できる」ことが、生業としてすごく幸せなことだなと感じました。生業が決まり、「養鶏にふさわしい住まい」も探し始めて、それで今、住んでいるところに落ち着きました。
※平飼い養鶏は、鶏が自由に動き回れる施設で行われる養鶏。鶏にとって砂遊び・地面探索など自然な行動環境で飼育できるなどのメリットがある。
――平飼いでの養鶏、どのような魅力があるのでしょう。
鶏の話は終わりませんよ(笑)。本当にね、鶏は一羽一羽に個性があって、皆さん「 一羽ずつ性格あるんだね![]() 」とびっくりされます。犬や猫と同じように、鶏も皆にそれぞれ個性があるんですよ。だから、養鶏も、それぞれの子に合わせて世話をしてるっていうのかな。こっちが 目を向けると、向こうも分かってくれるし、ちゃんとこちらの 思いも伝わるんです。単に卵を生む家畜っていうわけではなくて、私にとっては家族のような気持ちでいるんです
」とびっくりされます。犬や猫と同じように、鶏も皆にそれぞれ個性があるんですよ。だから、養鶏も、それぞれの子に合わせて世話をしてるっていうのかな。こっちが 目を向けると、向こうも分かってくれるし、ちゃんとこちらの 思いも伝わるんです。単に卵を生む家畜っていうわけではなくて、私にとっては家族のような気持ちでいるんです![]() 。大家族という感じです。
。大家族という感じです。

鶏が自由に走り回り、飛び回ることができる村内さんの養鶏場では、遊びまわる鶏の姿が当たり前の光景だ。
日本の養鶏は本当に課題がいっぱいなので、「むらたま」についての情報を発信して、それを皆さんに見てもらうことで、日本の養鶏について、少しでも理解を深めてもらいたいです。別にうちの卵買ってほしいという話ではなく、平飼い養鶏がもっと広まればと思っています。それから、平飼い養鶏を志す人も増えればいいなと思います。
昔の庭先養鶏みたいに、「卵を生むペットがいるよ」みたいな感じで、気軽に鶏を飼っていただける方が増えれば、もっともっと、この理解が広がりやすくなるかなと思っています![]() 。村のご年配の方々でも、「昔、うちにも鶏いたんだよ」と懐かしくお話される方が多いです。 自分たちが食べるもの、「命」というのかな。命の問題を、肩肘を張った食育という形でなくても、身近にいる生き物を食べているんだなというのを実感できればいいのになと思っています。
。村のご年配の方々でも、「昔、うちにも鶏いたんだよ」と懐かしくお話される方が多いです。 自分たちが食べるもの、「命」というのかな。命の問題を、肩肘を張った食育という形でなくても、身近にいる生き物を食べているんだなというのを実感できればいいのになと思っています。

自由に動き回れる鶏たちを増やすため、写真に写る空地にも養鶏施設を増築予定とのこと。鶏のお話をされるときの楽しそうなお顔が印象的。
――養鶏という新しいお仕事へのチャレンジ、大変なことも多いのではないですか。
仕事にこだわればこだわるほど赤字が膨らみます。なので、どこまで赤字に耐えられるかという部分は大変ですね。あまり妥協すると、こだわりを持って養鶏を生業にしている意味がなくなります。効率化していけばすぐに黒字になるんですけど、それは私がやりたい養鶏ではないですからね。なかなか黒字にはなりませんね(笑)。
――鶏への負担やストレスの軽減というアニマルウェルフェア(動物福祉)の視点を特に大切にされているとお聞きしていますが、手間暇のかかることも多いのではないですか。
本当に手間はかかるんです。餌にしても、普通は配合飼料というものを売っていて、それをやります。でも「むらたま」では、牡蠣殻以外の餌はすべて、自分で納得できるものを集めてくるんです。人間で例えると、定食屋さんに行って「○○定食ください」って注文して食べるのが一般的な養鶏。私の養鶏の場合は、まず畑に行って野菜を採って、それ洗って切って、自分で定食を作って食べるようなイメージです。それくらい手間の違いはあるんです。大変なことも多いですが、うちの養鶏場を見に来た方は「むらたまの鶏は幸せよね」って言ってくださいます![]() 。
。

飼料になる野菜などは、近隣の方々からいただいています。専業農家の方もいらっしゃるし、そうじゃない方もおられます。「新米ができたから去年の米、使っていいよ」という感じで。今は鳥が卵を産まない時期なので、卵でお返しできないんですけど、卵を産む時期には、はね出し(B級品)が卵にもあるので、そういったもので飼料をいただいている方にお礼をしています。物々交換ですね(笑)。

鶏を第一に考える村内さんの養鶏に共感する方も多い。野菜や穀類などのこだわりの飼料も、村内さんの人脈の賜物だ。
【村内さんの「平飼い卵」にご興味のある方はこちら】
Instagram:https://www.instagram.com/muratama2019/
――いろいろな方とつながりがあるんですね。お仕事以外で、村での人付き合いも多いのですか。
高山村は割と地域ごとのつながりの単位である「区」で寄り合いが多くて、 行事も結構多いです。皆、顔見知りというか、よくお互いにわかっている感じなんですよ。もちろん、それが嫌っていう方もいると思うんですけど、私はいいなと思っていますし、暮らしやすいですよ。病院にかかるときなども、「どこどこの眼科、いいよ!」って地域の方から教えてもらったりもしますよ。
一つ難を言えば、清掃などの共同作業がある時に、一世帯から一人、人を出すんですよ。うちは単身世帯なんで、絶対私が出ます。そんな時は、「鶏よ、ごめん![]() しばらく自分たちでやってくれ
しばらく自分たちでやってくれ![]() 」って言って出てきます(笑)。
」って言って出てきます(笑)。
※高山村に限らず、道路の草刈りや補修、一斉清掃などを年に数回、住民が総出で行う風習が残っている地域は多い。地域によっては行事に欠席すると「出不足金」とよばれる負担が必要な仕組みになっていることもある。
――困ったこともコミュニティが解決してくれるといった感じですね。
先ほど「区」のお話をしましたが、それ以外のコミュニティとして、仕事柄、農家などの生産者さんと知り合う機会が多いんですよ。養鶏に対する考え方が私と近い方々とつながりもできてきて、高山村に限らず、信濃町や中野市の方ともつながっています。
10月まで、鶏の環境に配慮した養鶏施設を増築するためにクラウドファンディングをやっていたんですが、その時も、いろんな方が応援してくださいました。皆さん、利害関係とかではなくて、本当に家族という感じで応援してくださったので、ありがたかったです。
~特別豪雪地帯!雪国『高山村』~
――2016年に移住されたとお聞きしていますが、冬の寒さは慣れましたか。
高山村くらいの寒さは全然平気ですね![]() 。実は昔、中国やカザフスタン、ウズベキスタンに住んでいたことがあるんです。以前住んでいた中国東北部の地域は冬場、氷点下20度くらいになりましたし、それと比べればびっくりもしません(笑)。でも雪かき
。実は昔、中国やカザフスタン、ウズベキスタンに住んでいたことがあるんです。以前住んでいた中国東北部の地域は冬場、氷点下20度くらいになりましたし、それと比べればびっくりもしません(笑)。でも雪かき![]() は嫌だけど
は嫌だけど![]() 。
。
――そんなに寒いところでお住まいの経験があれば、冬に心配はありませんね。でも雪はやっぱり大変なんですね。
最初は雪もすごく嬉しかったんですよ。雪が積もっても「やったあ![]() 雪だ
雪だ![]() 」みたいな。でも、早めに雪かきしないと重くなってしまう、硬くなってしまうということを学びました…。今は雪が降ったら、「とにかく、まずは雪かきだ
」みたいな。でも、早めに雪かきしないと重くなってしまう、硬くなってしまうということを学びました…。今は雪が降ったら、「とにかく、まずは雪かきだ![]() 」という感じですね。
」という感じですね。

冬は雪深く、村落部でも40センチ以上の積雪が見られる高山村。生活道路は除雪も行われるため安心。(写真提供:高山村)
~移住者、村内さんの語る高山村の魅力~
――『高山村』の環境がすごく良いというお話が冒頭ありましたね。長野地域は、自然環境に魅力を感じて、子供のいる世帯やリタイア後の方が移住されるケースも多いようですよ。
高山村に住み始めて最初に感動したのは、朝、鳥の鳴き声で目が覚めるんですよ。だんだん空が明るくなってくると「ピチピチ、ピチピチ」って鳥が鳴き始めて、「ここは別荘地![]() 」みたいな感想でした。すごく幸せなことだと思います。高山村が地元の方は、「どこがいいんだ?」って仰ることもありますけれど、毎日のことだから慣れてしまっていると思うんです。地元の方は当たり前だと思っているかもしれないけれど、高山村は写真を撮れば全部が絵葉書になりますよ。それが毎日の暮らしにあるわけです。
」みたいな感想でした。すごく幸せなことだと思います。高山村が地元の方は、「どこがいいんだ?」って仰ることもありますけれど、毎日のことだから慣れてしまっていると思うんです。地元の方は当たり前だと思っているかもしれないけれど、高山村は写真を撮れば全部が絵葉書になりますよ。それが毎日の暮らしにあるわけです。

高山村の名勝「雷滝」は、雷鳴のような轟音で流れ落ちる高さ30mの滝を間近で見られる絶景スポット。滝を真裏から眺めることができるため「裏見の滝」とも呼ばれる。
――『高山村』を含め、長野市周辺9市町村の長野地域、村内さんから見てどんな地域でしょう。
良い意味で開発されていない。昔ながらの日本の良さが残っている。風景にしても、自然にしても。そういう魅力は外国人に対しても訴求できるところだと思います。でも、県庁の方(インタビューア)に言うのもあれですが、ちょっとPRが下手かな![]() 。ゲストハウスにいた時も、外国人の方々たくさんいらっしゃったんですけど、大体、渋温泉の猿を見て帰ってしまう。なんかもったいないなって思いながら見ていました。
。ゲストハウスにいた時も、外国人の方々たくさんいらっしゃったんですけど、大体、渋温泉の猿を見て帰ってしまう。なんかもったいないなって思いながら見ていました。
――北陸新幹線も金沢まで開通し、長野県は西日本、東日本のいずれからも観光ルートに組み込まれるようになりましたね。観光客への訴求ももっと考えないといけないところです。さて、『高山村』についてですが、その魅力を一言でお願いします。
何回も言ってしまいますが、『ちょうどいい田舎』です![]() 。
。
――『ちょうどいい田舎』、そんな『高山村』で村内さんが特に好きな風景やスポットはありますか。
いっぱいあるので「特にここ」って言われると困っちゃうなあ。信州たかやまワイナリーからちょっと上がったとこなんですけど、そこから善光寺平がすごくよく見えるんですよ。そこだとワインブドウ畑の向こうに善光寺平が見えるので、高山村らしい風景です。
あと、高山の五大桜ってご存知ですかね。枝垂れ桜やエドヒガン桜の巨木で、開花時期になるとライトアップされて、夜景と一緒に楽しめます。もちろん昼間もすごく美しいですよ。五本のうちの、水中(みずなか)の桜は、吉永小百合さん主演の映画にも出ています。

――『高山村』の魅力、いろいろお聴きすることができました。村内さんの中で、移住して良かったこと、もう少しよくなればいいのになというところ、二面的な見方で教えてください。
本当に、第二のふるさとのような居心地の良さがあります。これは移住してよかったなって。 最初にピンと来た、「風景」、「環境」、「人」、そのインスピレーションに間違いはなかったっていう感じです。ふるさとになったなっていう気がしています。
本当に古くからのいろんなものが残っている地域なんですが、それを存続させたいと思いつつ、 担い手は減っているので、若者たちが村へ戻ってきたいと思うような、また、村出身じゃない方たちが住みたいと思うような場所にするにはどうしたらいいのかなと考えてしまいます。
それから、移住を希望している人には何度か来てもらって、馴染んでもらって、本当にいいところだなって思ってもらわないと、なかなか定住は難しいのかな。私は結果的に二段階移住※でした。二段階移住をもっと考えてもいいのではないかと思います。 ピンポイントでまず高山村を選ぶ人は、そんなに多くはないと思います。とりあえずここに住めますよといった二段階移住の拠点があったらいいなと思います。
※地方移住や田舎暮らしの希望者に対し、まず地方の中でも都市部に移住してもらい、自分に合った移住先をじっくり探してもらう移住の在り方。高知県などで取り組みが進んでいる。
~悔いのない移住をするために~
――それでは最後に、『高山村』に限らず移住を考えている方に向け、ご自身の経験などからメッセージをお願いします。
そうですね。「なんとかなる。」、だから「楽しむ。」ということが大事だと思います。無責任発言ですみません。
人生は1回きりなので、 「今がすごく大変」っていうことがあっても、後々は笑えると思って乗り切っています。あれもこれもと考えて、石橋を叩きすぎると、前へ進めなくなってしまうかもしれない。ひとまず、「ピンときたら」、「ああっ、これは!」と思ったらやってみる。それでやっぱりダメだよなって思えば、また戻ればいい。道は一つだけでなく、きっと違う道もあると思っています。移住する時も、まずは「いいかも」と思ったら、飛び込んでみるのもいいのではないでしょうか。
――人とのご縁やつながり、直感を大切に移住の選択をされた村内さんのお話、興味深かったです。養鶏のお仕事もどうぞ頑張ってください。本日はありがとうございました。
【制作】長野県長野地域振興局 【協力】村内倫子さん・高山村定住支援室定住支援係
〈長野県高山村への移住に関するお問合せ先〉
高山村定住支援室定住支援係
【電 話】026-214-9298 【メール】teiju@vill.takayama.nagano.jp
【ホームページ】https://www.vill.takayama.nagano.jp/kanko/iju/
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
長野地域振興局 総務管理課
TEL:026-234-9500
FAX:026-234-9504