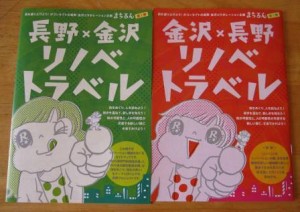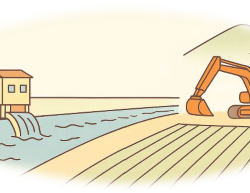2015.10.05 [ 子ども・若者長野地域の【暮らし】 ]
長野門前大学6時間目は、「日本茶学」
こんにちは、地域政策課のmです。
平成27年9月27日(日)、善光寺大門の「中央館 清水屋旅館」で、「NPO法人長野門前創造会議」が主催する「長野門前大学」の6時間目の講義、「日本茶学」が開催されました。
「長野門前大学」とは、長野市善光寺門前界隈で暮らしたり、働いている人たちから様々なことを学ぼうと、まち全体をひとつのキャンパスに見立てた企画で、4月から毎月1回、開催されています。
今回の会場は、善光寺大門の「中央館 清水屋旅館」。160年以上の歴史を持つ純和風旅館です。折りしも今宵は中秋の名月。老舗旅館の風情を感じながら、月を眺め、美味しいお茶とお菓子をいただきます♥
★主催している「NPO法人長野門前創造会議」について、もう少し触れてみます。
「NPO法人長野門前創造会議」は、善光寺門前でリノベーションに携わった有志が、門前の新名所や旧跡をまち歩きで一緒に巡る楽しさを発信することで、門前を訪れる人を増やし、まちの活性化につなげたいと、平成26年12月に設立された法人です。
平成26年度地域発元気づくり支援金を得て、平成27年2月には長野と金沢のリノベーションによる施設を掲載した、まち歩き情報冊子「まちるん」を、金沢のNPO法人と共同で発行しました。
3月の北陸新幹線金沢延伸開業によって1時間で結ばれた、長野と金沢。お互いの交流が活発になるように、期待も込められています。
平成27年度は、「まちるん」の作成を通して繋がりができた門前の店舗や職人の人達に講師になってもらい、門前に足を運んで寺町ならではの文化を体験して欲しいと「長野門前大学」を企画。平成27年度地域発元気づくり支援金を得て、4月から毎月1回の講座が始まっています。すでに、「ウイスキー学」「シルク学」「座禅&ヨガ学」「クラフトビール学」「善光寺学」など、様々な講座が行われてきました。
9月の6時間目は「日本茶学」。講師は長喜園店主の宵野間信行(よいのまのぶゆき)さん。日本茶インストラクターの資格を持つ宵野間さんにより、『なぜ永きに渡りお茶は飲まれてきたのか?』をテーマに、お茶の原産地、日本の茶の歴史、茶の種類などのお話から始まりました。
お茶は、発酵させない緑茶、半発酵のウーロン茶、発酵させる紅茶など、チャの樹の葉の加工方法によって多くの種類の茶ができます。
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
長野地域振興局 総務管理課
TEL:026-234-9500
FAX:026-234-9504