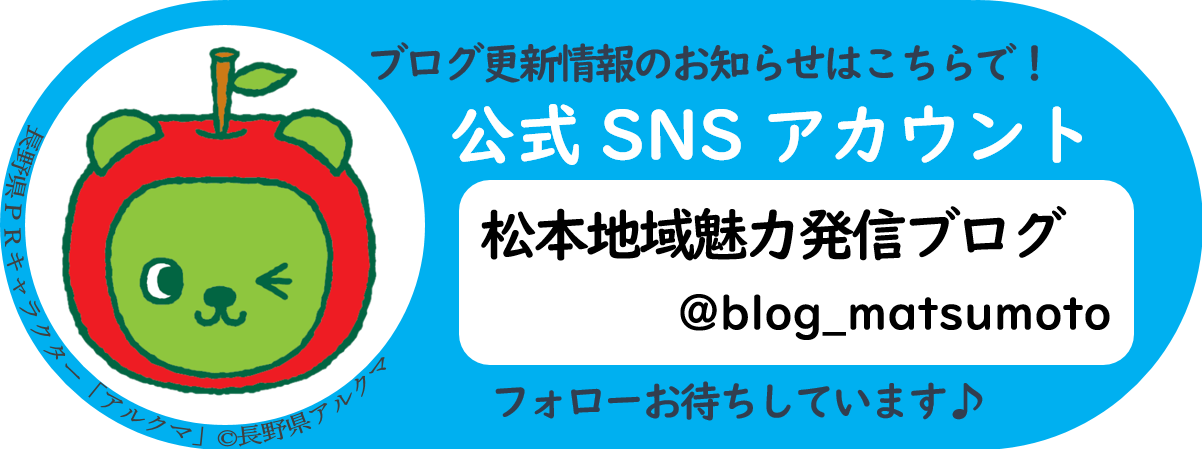2014.10.27 [ 自然・観光地 ]
地域の利水の実態を学ぶ「水巡りアクアツアー」が開催されました!(前編)
今年の7月、ダムの貯水率が22%にまで落ち込むということがありましたが、その後の雨などで
現在は100%になっているとのこと。まさに恵みの雨だったんですね\(^^)/![]()
奈良井川の最上流はこの先20kmほど先にある標高2653mの茶臼山。その1滴が奈良井川となり
犀川に合流し千曲川(信濃川)に合流して海へと流れます。その長い流れの中で水は多くのひとに
使われています。川の水を大切に、きれいな川を保ち続けることの重要性を再認識できました。
奈良井ダムの次は長野県企業局松塩水道用水管理事務所で、この奈良井川の水(原水)から私たちが
いつも飲む安全な水(浄水)へときれいにしていく過程の視察です![]()
松塩水道用水管理事務所では、毎日81000㎥(プール216杯分)の水が作られ、松本市・塩尻市・山形村の
約23万人がその水を使用しています。想像もつかないとても膨大な量ですね(><)!
2つ班に分かれて、管理事務所の今井さんと金井さんの説明を聞きながら各施設をまわっていきました。
始めは着水井(ちゃくすいせい)。奈良井川の水が一番初めにやってくるところです。
写真でもわかるように、この段階でもきれいな水ですが台風などがあったときには茶色く濁って
しまうそうです![]() ここから薬品混和池を経てフロック形成池に送られます。
ここから薬品混和池を経てフロック形成池に送られます。
薬品混和池ではポリ塩化アルミニウムという薬品を入れ、フロック形成池で水中の羽根車を回すことにより、
泥やゴミが互いにくっつきあって泥のかたまり(フロック)が作られていきます。
参加者の皆さんと一緒に水中に目を凝らすと、小さなフロックが確認できました![]()
フロック形成池の水はとなりの長さ67m×幅13m×深さ4mもある巨大な薬品沈殿池に流れます。
この池で4時間かけてフロックは沈んでいき、池の入り口付近では底が見えなかった水も
池の出口付近でははっきりと底が見えるまでに透明度が増していました![]()
工事期間とあって、普段は見られない水のない薬品沈殿池も見ることができました。
沈んだ泥たちは、毎秒13mmで動く泥かき寄せ機でゆっくりゆっくりと集められていきます。
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
松本地域振興局 総務管理課
TEL:0263-40-1955
FAX:0263-47-7821