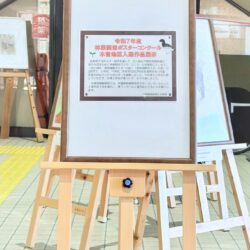総務管理・環境課のとうふです。
第21回の今回は、木曽路全体の中でも上位にランクインするであろう観光スポット、妻籠宿をお届けします!
が、端から一つ一つ紹介していくと紙幅が大変なことになるので、いくつかのポイントにまとめて書いていきます。
① 町並み
妻籠宿を象徴するのは、大切に保全された町並みです。

妻籠宿は国の重要伝統的建造物群保存地区に最も早く選定された場所の一つであり、公式HPでは「全国に先駆けて保存運動が起こった」と紹介されています。
その町並みを歩くと、現代風の建物がほとんど視界に入らず、江戸時代末期へタイムスリップした感覚になります。
特に、保存運動の始まりの場所となった「寺下の町並み」は、標識すらも最小限に、目立たないものが設置されている印象です。
「景観に余計なもの」が極力排された絶好の写真スポットが、ここ妻籠宿 寺下ではないかと思います。

私の記事ではほぼ毎回取り上げる宿場の定番、枡形も、妻籠宿の中間付近にしっかり残っています。
ちなみに、この古き良き日本の宿場風景を最大限に味わえるのが、「文化文政風俗絵巻之行列」です。
その様子は過去のブログでも記事にしていますので、こちらやこちらをご覧ください!
② 残っている民家
これまで通ってきた宿場でも、古い建物は数多く残っており、中を見学できるところも複数ありました。
しかし、それらの多くは本陣など宿場の施設や旅籠(旅館)、商家などで、「ごくごく普通の民家」はあまりなかったように思います。
妻籠宿には、そんな民家が残っており、中を覗くことができます。
上2枚「熊谷家住宅」
「下嵯峨屋」
これらは長屋の一部が残され、民家として使用されていたものだそうです。
土間と、居住空間が数部屋のみ。軒が低く、広いとは言い難い家ですが、当時の庶民の暮らしぶりがうかがえる貴重な歴史資料です。
③ 本陣・脇本陣
妻籠宿には、本陣と脇本陣がそれぞれ復元、現存の形で存在しています。


本陣は一度取り壊されたものの、江戸時代後期の間取りが忠実に復元され、公開されています。
部屋数も広さもかなりのもので、身分が高い人の宿泊所である本陣の格の高さが感じられます。


脇本陣は、明治時代に建て替えられた建物が現存しています。
明治天皇もここで休息を取られたようで、明治天皇使用の机も残されていました。
中に入るとガイドの方に解説をいただけますが、こちらも興味深い話ばかりで…建物の隅々まで見どころ満載なことがわかります。
書き始めると終わらないので、ぜひ現地を訪れて解説を聞いてみてください!
ちなみに、冬の妻籠宿を象徴する、囲炉裏に日差しが差し込む光景は、ここ脇本陣で撮られています。
いかがでしたか?
宿場の面影を大変良く残し、見学できる場所も多く、一日いられる妻籠宿。
案外交通の便も悪くないので、皆様ぜひお越しください!
次回は「サムライロード」として多くの外国人観光客が歩く馬籠峠を越えます。
このシリーズもあと数回です。引き続きご覧いただけるとうれしいです!
前回に引き続き、散策時期は6月下旬です。
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
木曽地域振興局 総務管理・環境課
TEL:0264-25-2211
FAX:0264-23-2583