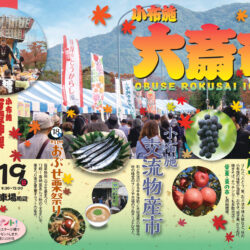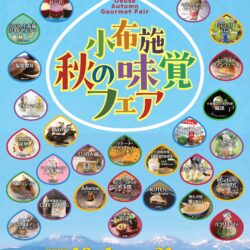皆さんこんにちは。長野地域振興局企画振興課のFです。今回は私が推したい休日のお出かけスポットとして、須坂市にある史跡、「八丁鎧塚古墳」をご紹介しようと思います。
須坂市を流れる鮎川の北方流域には古墳が多数存在し、鮎川古墳群と称されています。この鮎川古墳群の中でも特に有名なものが、今回ご紹介する「八丁鎧塚古墳」です。
教科書などで目にすることが多い大仙陵古墳(仁徳天皇陵)などをイメージしていただくと、古墳には木々が茂っている印象を受ける方も多いと思います。一般的に古墳は土を盛って造られることが多いです。しかし、長野県域では”積石塚古墳”とよばれる、主に川原石を積み上げて造られた古墳が多く存在しています。この積石塚古墳のうち、日本最大級の大きさを誇るのが「八丁鎧塚古墳」です。5世紀初め頃に築造されたとされており、朝鮮半島の墳丘墓と共通した特徴を持っています。
石積みの武骨な外観ながら、円形のフォルムは美しい曲線を描いています。原形を非常によくとどめており、積石塚古墳の構造を、間近で観察することができるのも、非常におすすめのポイントです。駐車場も整備されており、大変訪ねやすくもなっています。
この八丁鎧塚古墳、かの文豪”松本清張”が昭和36年に須坂高校へ講演に訪れた際、立ち寄ったというエピソードがあります。清張は古代史などへの知識造詣が極めて深く、邪馬台国論争を落とし込んだ『陸行水行』などの作品を描いていることは有名です。清張もまた、八丁鎧塚古墳を愛でながら、古代の日本や小説の構想に思いをいたしていたのかもしれません。
須坂市の鮎川流域をはじめ、長野地域には存外、多くの古墳が遺されています。お休みの日のお出かけに、観光に、1600年の歴史を体感できる古墳に足を運んでみるのはいかがでしょうか?
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
長野地域振興局 総務管理課
TEL:026-234-9500
FAX:026-234-9504