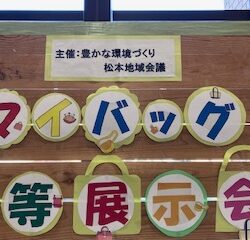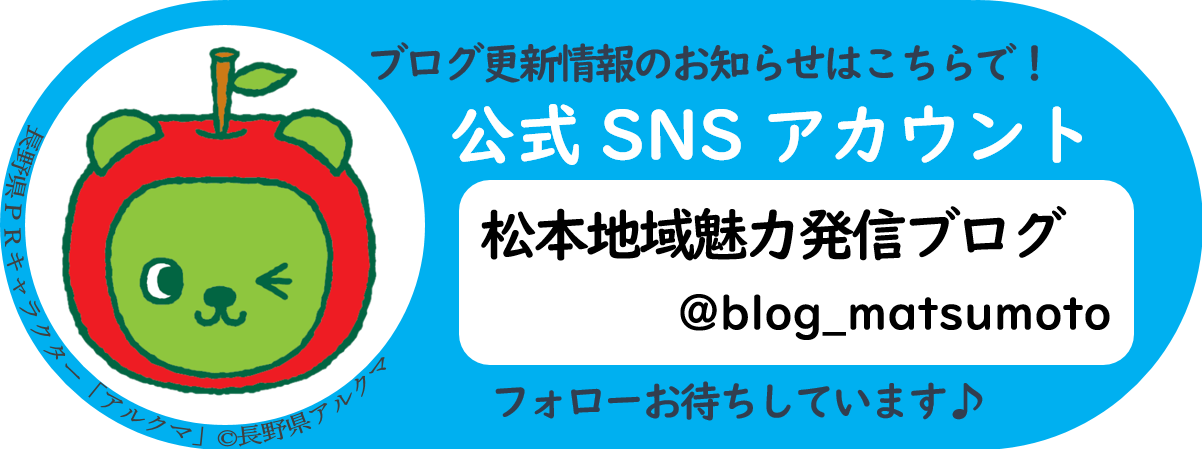↑牛若丸より「五条大橋 弁慶と牛若丸」
Yuzu&Bunnです。
今回は日頃参加している地域活動を紹介します。
冒頭の写真で紹介させていただいたのは、安曇野市三郷にあります住吉神社の御船祭りになります。
私は現在このお祭りの保存会の一員として人形師を担当しており、御船に飾り付ける武者飾りの製作から飾り付けまでを受け持っています。
穂高神社では3名の人形師の元、教室を開催するなどして後継者育成を図りながら製作をしていますが、当地域ではこうした専属の人形師はいないため、代々先輩から後輩へと技術の継承が行われてきました。

↑大人が実際に着用することができます

↑牛若丸の水干(上着)はシーツを使って自作してます
祭り準備が始まるとその年飾り付ける場面に必要な甲冑や小道具を製作していきます。
甲冑や刀はもちろんのこと、弓矢や陣幕など多岐にわたります。
もちろん本物を買うような予算はありませんので、ホームセンターなどで完成イメージに合った材料を仕入れ自作していきます。
必要に応じて着物を縫ったりもしています。
中でも一番時間を要するのは甲冑です。
現在使用している素材はプラスチックと甲冑紐と呼ばれる平紐で製作していますが、私が最初に教わった頃は段ボールと毛糸で製作していました。製作方法も時代とともに変化しています。
材料こそ違うものの、糸の縅(おどし)方などは本物と同じやり方で縅していくためフルセットで製作するには2ヶ月以上の期間を要します。
着付の終わった人形は、祭り当日御船に飾り付けてお披露目です。
見学に来てくれた方から今年の飾りは良かったと言われるのは人形師として嬉しい瞬間です。

↑飾りつけを終えて展示されている御船
今回は人形飾りについて紹介しましたが、保存会では子供の太鼓指導などを行うお囃子班、御船の装飾全般を受け持つ飾り班などの役割がありそれぞれ当日に向けた準備を進めています。
4月の終わりには本年の御船祭りが執り行われます。
地域の方々が力を合わせて作り上げる御船を是非ご覧ください。

↑この御船の象徴「唐獅子牡丹」は平成21年に再調された新しい幕です
また、安曇野市豊科郷土博物館では、大正時代に新調され平成21年の御遷宮にあわせて再調されるまで住吉神社で実際に使われてきた御船の幕が常設展示されております。
幕の横に立ちその大きさを体感してみてはいかがでしょう。
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
松本地域振興局 総務管理課
TEL:0263-40-1955
FAX:0263-47-7821