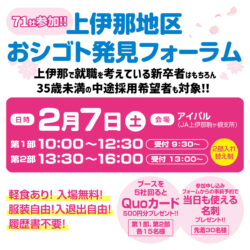2025.11.18 [ その他 ]
「特別支援教育をもっと身近に感じてほしい~長野県伊那養護学校の取組~」
どすこい太郎です。
本日は特別支援教育の現状とこれからについて、長野県伊那養護学校の梶谷教頭先生にインタビューしました。
記事内では、梶谷先生を「梶」、筆者(どすこい太郎)を「ど」と表記しています。
長野県伊那養護学校(伊那市)について・・・
昭和41年4月1日に長野県伊那養護学校として開校して以来、「優しさと確かさに溢れた学校」を学校像として60年近く上伊那地域における特別支援教育の責務を果たしてきました。
学校の目標は「自分から 自分で 精いっぱい そして いっしょに」。
なお、学校教育法の一部改正に伴い法令上は特別支援学校に統一されていることや、特別支援教育の理念の一層の理解促進を図るため、これまでの長野県伊那養護学校から長野県伊那支援学校へ校名が令和8年4月1日から変更となります。
詳細な内容はホームページで御覧になれます(https://donguri-inayo.ed.jp/)。
1 長野県伊那養護学校について
ど 伊那養護学校の児童(小中学部生)・生徒(高等部生)在籍数や御校の特徴を教えてください。
梶 令和7年度の在籍数では、小学部78人・中学部39人・高等部103人、その他後程説明しますが分教室などにも在籍者がいます。(上記の在籍数のうち、小学部はなももの里分教室が9人、中学部分教室友組が10人、高等部中の原分教室が14人)
最近の傾向として、小学部1年生の在籍数が20人となったため初めて3クラス編成となるなど、子ども一人ひとりのニーズに応じた教育を提供しています。
「養護学校」についてあまり馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、各市町村の教育委員会に設置されている就学支援委員会(教育、行政職員などで構成)において、障がいのある子どもの実態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえ、総合的な観点から特別支援学校での就学が適当と判断された子どもが在籍することとなります。
 本校の特徴として、在籍児童生徒には個々のニーズに応じた学びに加え、生活及び進路支援、副学籍交流などの地域連携などの支援体制を構築する「伊那養専門性サポートチーム」として体制を整えており、全職員がチームとなって子どもたちとその活動を支えています。
本校の特徴として、在籍児童生徒には個々のニーズに応じた学びに加え、生活及び進路支援、副学籍交流などの地域連携などの支援体制を構築する「伊那養専門性サポートチーム」として体制を整えており、全職員がチームとなって子どもたちとその活動を支えています。
また、各市町村において交流提携校となっている小中高校(以後、「提携校」と記載します。)と年数回交流する機会や、上伊那8市町村全てで整えられた副次的な学籍制度を活用した副学籍交流も行われています。
ど お話の中にありました「副学籍」とはどういった制度なのでしょうか。
梶 「地域の子は地域で育てる」という理念のもと、養護学校(特別支援学校)に通う子どもたちの副次的な学籍を居住地の小中学校に置いて、地元の友だちとのつながりや地域での存在感を支える仕組みを制度化しています(※1)。
この制度は、平成17年に駒ヶ根市が「副学籍」という名称で取り組んだのが始まりで、徐々に駒ヶ根市周辺の市町村に広がり、平成25年には上伊那圏域8市町村全てで「副学籍」が整えられ、令和7年には長野県内全ての市町村で副次的な学籍が導入されました。
ど 養護学校に通学しながら引き続き副次的な学籍のある地域の学校の行事や学習に参加することもできる制度が上伊那から全県に広がったということですね。
梶 他地域に先んじて、本校に通う全ての児童生徒は地域学校への副学籍を整えていただいています。
2 特別支援教育の現状とこれからについて
ど 御校についてお伺いしてきましたが、この取材では現状での課題やこれからの展望などについてもお伺いしており、それらについて御意見をお聞かせください。
梶 本校では生徒数が増加傾向のため、教室不足に対応するため新棟を建築して令和6年3月に完成しました。
県の見込み(※2)として、今後も養護学校への希望者は、緩やかですが右肩上がりで増加するものと考えており、本校も今年度の小学部新1学年は初めての3学級編成となりました。年度によってかなり人数にばらつきはありますが、増え続けるようであればまた教室が足りなくなるのではと心配はしています。
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
上伊那地域振興局 総務管理課
TEL:0265-76-6800
FAX:0265-76-6804