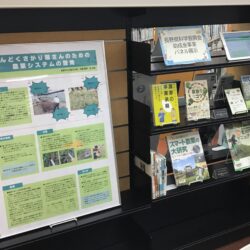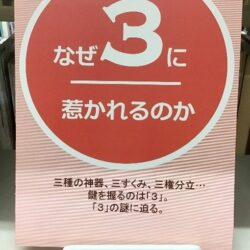2025.07.08 [ 山好き館長の信州便り ]
聞く・触る・見る本、いかがですか?(FMぜんこうじ「図書ナビ」第28回)

本日ご紹介する本たち
みなさま、こんにちは。県立長野図書館の森です。FMぜんこうじの「ひるどきもんぷらワイド」、 2025年7月8日(火)に放送された「図書ナビ」コーナー、第28回目の内容をご報告します。昨日は令和7年7月7日ということで、記念日にしたいと入籍した人も多かったのだとか。7月初旬だというのに、熱中症が心配な今日この頃ですが、オープニングの一曲は、そんな暑ささえも楽しむ気持ちになれる『ブラジルの水彩画』でした。
本を読むことの障壁とは?
中川さん:早いもので今年ももう折り返しですね。そう言えば、先日の新聞に「読書のバリアフリーを考える」という催しの様子が載っていましたね。
森:はい。おかげさまで、信濃毎日新聞さんやテレビ信州さんからも取材をしていただいて、有難かったです。「バリアフリー」とは、社会で生活していく上で、バリア(障壁)となるものを、フリーにする(なくしていく)という意味です。その中でも、「読書バリアフリー」は、本を読むことについての障壁をなくすことを目指しています。2019年には、読書バリアフリー法という法律も成立しているんですよ。
中川さん、「本を読むことの障壁」って、どのようなことがあると思われますか?
中川さん:ずっとまえ、本の「音訳ボランティア」ということを聞いた時に、なるほどと思ったのを覚えています。あとは、2年前の芥川賞を受賞された『ハンチバック』からは沢山の気付きが得られました。
森:ありがとうございます。市川沙央さんが『ハンチバック』(「せむし」という意味)で芥川賞を受賞された時の挨拶は、強い言葉で紙の本が読めない立場からの訴えがあり、衝撃的でしたね。
中川さん:「やっぱり紙の本は良い」と思っていましたし、良さはもちろんあるんですが…
森:いろんな読書の手段があってほしいと思わせられましたよね。電子書籍の発行を許諾する作家さんや出版社さんが増えたようです。
読書バリアフリーって何だろう
森:先日、県立長野図書館で開催したイベントは2つありました。
1つは、「読書バリアフリーって何だろう?」ということを知る、交流形式の研修会。全国各地で読書バリアフリーの普及を推進する「りんごプロジェクト」から講師の方に来て頂いて、お話をうかがいました。
実は、県立長野図書館で「読書バリアフリー」を担当している職員さんたちが、「担当になったけれど、何をしたらいいんだろう?」と迷子になりかかっていた時に、「りんごプロジェクト」の方のお話を聴く機会があって、「道筋が見えた!ほかの方にも知ってほしい」という想いで企画してくれたんです。
「りんごプロジェクト」というのは、誰もが自分にとって読みやすい、アクセスしやすい、=アクセシブルな本について、知ってもらうためにスウェーデンでうまれた取り組みです。いろいろなバリアを解消できる、読みやすい本を集めた「りんごの棚」を作る図書館も増えているんですよ。
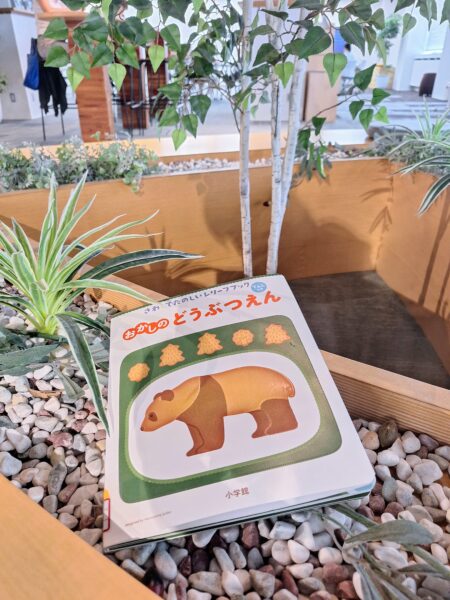
点字付き絵本
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
県立長野図書館 総務企画課
TEL:026-228-4939
FAX:026-291-6252